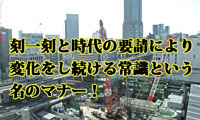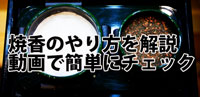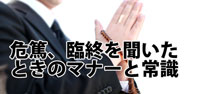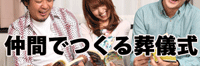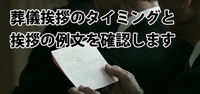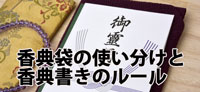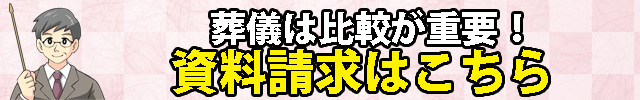お葬式は日常行事ではないものの、日本古来の文化が根付いていてマナーやルールがたくさんあります。葬儀の参列は気持ちなので献花も気持ちさえされば良いですが、基本的なマナーを知っておくことも重要でしょう。
お葬式は日常行事ではないものの、日本古来の文化が根付いていてマナーやルールがたくさんあります。葬儀の参列は気持ちなので献花も気持ちさえされば良いですが、基本的なマナーを知っておくことも重要でしょう。
隣の人や前の人のマネでなんとかなりますが、作法等々の話をしていきます。
 葬儀アドバイザー 佐々木
葬儀アドバイザー 佐々木 献花のマナーは葬儀よりお別れの会などで役に立つでしょう。
献花とは

献花の献とは、『たてまつる』『ささげる』の意味で、上位者や神仏にものをさしあげる。
近年日本の葬儀の形態も様変わりしてきており、仏教の葬儀ではお焼香をして故人の冥福を祈りますが、無宗教葬・音楽葬・家族葬・キリスト教葬などでは白い花を基調とした花などをお焼香の代りに、祭壇・献花台に故人の冥福を祈り花を捧げる葬儀の形式も増えてきております。
神道では榊を献花とします。基本的に焼香も献花も故人に対する偲ぶ心の思いの表現であり供養なのです。
献花に使われる花は?
白い「百合、カ-ネーション、マーガレット、菊」などで、淡い色のお花も近年使用されております。
キリスト教でない限り、故人の好きであった、色花を飾る方も増えてきております。数年前までは、棘のある薔薇は使用しない風習でしたが、棘の部分をカットした、色とりどりの薔薇を使用する方も増えております。
献花のやり方
一般的には献花と呼び、神道では玉串奉奠と呼び、手順はどちらも同じと考えて下さい。



- 順番が来たら花を受け取りますが、手のひらを上にした右手の方に花がくるよう、左手で茎元を上から軽く掴むように受け取るのが正式な持ち方です。
- 受け取った後、花を胸の高さに捧げ持って献花台に進み霊前に一礼します。
- 献花台の前で、花を時計回りに回して、茎元を霊前に向けて献花台に捧げます
- 献花が終わったら2~3歩退き、合掌胸の位置で両手を合わせて一礼します。
- 司祭に向かって一礼し、遺族に対しても一礼して、元の席に戻ります。
献花をする際の注意点として、献花台に奉げる時の両手の位置は、最初に受け取った時の形のままではなく、花を回す時に花が右手のひらに乗るよう、花側を軽く持ち、また左手は茎の中央部分を下から支え持つようにして献花をします。
礼拝をする際は、キリスト教信者は十字を切り、両手を組み合わせて礼拝しますが、一般の人は合掌・一礼で構いません。
神道の玉串奉奠の作法では、玉串は根元の方を右手、枝先の方を左手で受取り、右に回し根元を祭壇に向けて置きます。
このあと二礼二拍手一礼ですが、拍手はしのび手といって音をたてないようにしましょう。献花するお花は葬儀社で用意しておりますので、そのお花で献花しましょう。但し仏教徒であっても、念珠は基本的に使用しませんが、左手に念珠を持ち同じ動作でも構いません。
動画で献花の方法をチェックしましょう
花の種類は?
葬儀では、様々な場面でお花を使用します。同じ花でも呼び名が違いますので、この機会に覚えておいてください。
| 献花 | 上記したように、焼香の代りに使用する花で、一本祭壇に献上します。葬儀社で用意する花で基本、柩には納めません。 花の香り・お香の香りをお供えして、供養するもの。 |
|---|---|
| 枕花 | 故人が自宅に戻られたとき、最初にお供えするお花。花瓶にさす花でも・かご花でも構いません。但し土に植えたものでないこと |
| 花環 | 式場の外に飾る花でお名前を付けます。関東では造花(缶詰を添える地域もあり)・関西では、しきみ |
| 供花 | 親戚・友人・会社などの方が供えるお花。近年ご芳名板にお名前を付け祭壇脇に供える方式が増しました。 |
| 生花祭壇 | 祭壇には、白木祭壇・生花祭壇とがあり、花で祭壇を造ったものの事。 |
| 花束 | 出棺のとき、棺の上にお供えします。 |
| 別れ花 | 出棺のとき、棺の中に納めます。(生花祭壇・供花の花を使います)茎は使わずに花の部分だけを供えます。 |
| 忌明け花 | 亡くなられた日を含め、7日毎にお花を変え、供えます。四十九日まで |
※火葬所は、それぞれの地域でしきたりが違います。花束を柩と一緒に炉に納める場所もあれば、炉前の花瓶にさす場所もあります。通常花束は下の茎の部分に湿らしたガーゼを巻きその上をアルミ箔で包みます。炉は現在大半が電気炉のため、炉を壊してしまう事もありますので、くれぐれもアルミ箔を巻かない様にしましょう。